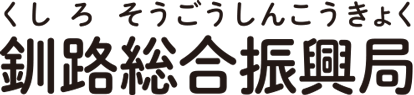令和7年度の収穫について
標茶町および弟子屈町の飼料用とうもろこしの収量調査結果を表1に示します。
表1 R7年収量調査結果

今年度は、は種作業は降雨により遅れたものの、その後の生育は順調に進みました。気温が平年より高く推移したため、登熟は順調に進み、標茶町では平年より12日早く、弟子屈町では13日早く、黄熟期に達しました。しかしながら、9月13~14日にかけて通過した低気圧による風雨の影響により、多くのほ場で倒伏(折損・なびき)が発生しました。
倒伏したほ場から収穫された飼料用とうもろこしサイレージの傾向と、給与する際の注意点を紹介します。
切断長のバラツキが大きい
倒伏した状態での収穫により、切断長のバラツキが大きくなります。飼料の粒度を確認するふるい(パーティクル・セパレーター(写真1))で昨年収穫のサイレージと、今年の原料草の粒度を比較しました(写真2)。

写真1 パーティクル・セパレーター

写真2 粒度の比較
昨年産のサイレージと比較すると、上段および下段の割合が増加し、適度な長さである中段は減少しました(表2)。
給与開始の際は、牛の反芻行動や糞の状態をよく観察しながら、給与量の調整を行いましょう。
表2 R6年収穫のサイレージとR7年原料草の粒度の比較

発酵品質に注意
倒伏した飼料用とうもろこしは、土砂等の付着やカビ発生のリスクが高まり、サイレージの不良発酵の一因となります。
サイロ表面をよく確認し、変敗箇所は取り除いて給与しましょう。また、粗飼料分析を行い、発酵品質を確認しましょう。
サイレージの品質や、軟便の発生状況によっては、カビ毒吸着材や生菌剤等の添加物の活用を検討しましょう。
この情報は2025年12月に地域(弟子屈町・標茶町・釧路町)の農業者向けに発出した技術情報です。